「法律を変えずに」ベーシックインカムを導入したら日本は財政破綻するのか?結論と試算
要約:
既存の年金・医療・生活保護などを一切いじらずに、ベーシックインカム(BI)を上乗せ導入すると、歳出が数十〜百兆円規模で恒常的に増え、財政の持続可能性は急速に悪化します。
日本は自国通貨建て債務のため即時デフォルトの可能性は低い一方、国債増発→金利上昇→国債費膨張→通貨安・インフレの悪循環リスクが大きく高まります。
結論(まずここだけ)
「法律を変えずに」=既存の社会保障制度を維持したままBIを追加支給する想定では、財政は実質的に持続不可能に近い。
ただし、法律を変えて税制・給付の統合や削減、増税・新税を組み合わせた代替導入ならば、設計次第で持続可能性を議論できます(本稿の結論は「上乗せ導入は厳しい」)。
前提の整理:「法律を変えない」とは何を意味するか
- 年金・医療・介護・生活保護・児童手当などの既存給付は全て現状維持。
- それに一律のBIを追加支給する(=制度の統廃合や削減は行わない)。
- 結果として、歳出は純増する。
ざっくり試算:BIの支給総額イメージ
支給コストは 「月額 × 12 × 対象人口」 で概算できます(全員一律支給の単純計算)。
| 月額BI | 年間コスト(全国民一律・概算) | コメント |
|---|---|---|
| 3万円 | 約44兆円 | 「控えめ」でも歳出の純増幅は巨大 |
| 6万円 | 約89兆円 | 一般会計税収規模(約70〜80兆円)に匹敵 |
| 10万円 | 約148兆円 | 単年での財源確保は現実的に極めて困難 |
※人口は約1.23億人規模を想定した概算。端数は四捨五入。実務は年齢階層・非居住者等の制度定義で変動します。
現状の歳出・税収との突き合わせ
- 一般会計歳出:おおむね100兆円超(社会保障・国債費が大きな比重)
- 税収:おおむね70〜80兆円レンジ
ここにBIの純増(例:6万円で約89兆円)を重ねると、歳出は一気に200兆円規模へ膨張。対して税収は追いつかず、恒常赤字の大幅拡大が不可避となります。
「財政破綻」になるの?—メカニズムで理解する
日本は自国通貨建て債務・中央銀行保有比率の高さにより、直ちに法的デフォルト(支払い停止)に陥る可能性は低いと考えられます。
しかし、赤字拡大→国債増発→金利上昇圧力→国債費膨張→通貨安・インフレという悪循環が強まり、実質的な「財政の行き詰まり」に近づくリスクは急上昇します。
よくある反論と押さえるべき論点
- 「BIで消費が増えて税収も増えるのでは?」
乗数効果や税収増は見込めても、数十兆〜百兆円規模の恒常支出を賄うには桁が合いにくい。景気循環に左右されやすく、恒久財源としては不安定。 - 「国債を発行すればよい」
長期・恒常の増発は金利上昇と国債費の雪だるま化を招きやすい。市場の信認という制約がある。 - 「インフレで実質負担を薄めればよい」
行き過ぎると実質賃金の低下・生活コスト上昇で逆効果。BIの実質価値も目減り。
導入するなら:持続可能性を担保する設計の方向性
以下はいずれも「法律を変える」前提ですが、現実に検討するなら不可避の論点です。
- 既存給付の統合・縮減:年金・児童手当・各種控除などを整理して財源中立に近づける。
- 税制改革:消費税・所得税・資産課税・炭素税などの組み合わせで安定財源を確保。
- 設計のメリハリ:対象限定(例:若年・子育て層中心)や金額抑制、段階的導入でマクロ衝撃を緩和。
- マクロ安定化策:金利・インフレ・為替に配慮した発行計画・ルールベースの財政運営。
簡易シミュレーター(考え方)
ご自身の前提で概算したい場合は、次の式を使えば1行で出せます。
年間BIコスト(兆円) ≒ 月額(万円) × 12 × 人口(億人)
例:月6万円 × 12 × 1.23億人 ≒ 約88.6兆円
まとめ
- 法律を変えずにBIを上乗せ導入 ⇒ 歳出が数十〜百兆円規模で純増し、財政は実質的に持続困難。
- 日本特有のファクターにより即時デフォルトは考えにくいが、金利・国債費・インフレ・通貨安のリスクは急上昇。
- 現実的に検討するなら、既存給付の統合・税制改革・支給設計の最適化を同時に進めることが不可欠。
※本稿は概算・一般論に基づく政策設計上の論点整理です。最新の予算・税収・人口統計は年次で更新されるため、実務シミュレーションでは直近データで再計算してください。

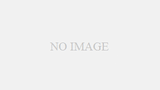
コメント